2025.08.25
今日のすぎのこ
「たべっ子どうぶつ」探し!!
夏休みも終盤に入りました。小学校は、間もなく2学期がはじまります。「宿題」の進み具合は、いかがでしょうか。jimjimが小学生だった頃は、「自由研究」というのがありまして、何でもいいから自分でテーマを決めてやってみるという宿題がありました。基本的に「自由」ですから、「工作」だったり「観察」だったり、さまざまなテーマが並びました。
jimjimが好きだったのは「昆虫採集」で、採集した昆虫に防腐剤などを注射して「標本」をつくるわけです。「蝶」は、羽から鱗粉が落ちないように注意しなければならず、採集の段階からちょっと難易度高めなので避け、セミやクワガタ、カブトムシなど比較的簡単に採集できる昆虫を集めました。セミですと「アブラゼミ」、「ミンミンゼミ」、「ヒグラシ」、「ツクツクボウシ」、「ニイニイゼミ」が主なメンバーで、そこに甲虫類から「カブトムシ」や「クワガタ」「カナブン」「コガネムシ」「タマムシ」などが加わって彩りを添えました。
これを現在にあてはめますと、セミの中からは「ヒグラシ」が消えて、そこに「クマゼミ」が入ることになるでしょうね。甲虫類では「コガネムシ」や「タマムシ」が消えてしまいました。「タマムシ」なんて、「幻の甲虫」といわれるくらい珍しくなってしまいましたが、jimjimが子どもの頃は、身近にたくさんいたんです。それだけ、自然が少なくなってしまったということでしょう。
「クワガタ」は、「コクワガタ」と「ノコギリクワガタ」の2種類がほとんどで、山間部に行った友人の標本には、ここに「ミヤマクワガタ」が加わり、「これがミヤマクワガタか、かっこいいなあ」と羨望を集めていました。実は、そのときから気になっていたことがあります。それは、「ノコギリクワガタ」についてのこと……。
jimjimが採集した「ノコギリクワガタ」には、「アゴ」が大きく湾曲した大型の「ノコギリクワガタ」と、それに比べて「アゴ」が小さく、からだも小ぶりな「ノコギリクワガタ」がいました。同じ「ノコギリクワガタ」なのに、なんでこんなにも姿が違うのだろうか……。それが、いままでずうっと抱いてきた疑問でした。
その疑問がきょう、解明されたんです。そのきっかけとなったのが、何度かご紹介したお子さまたちによる「虫の模写」でした。

その場面が、こちら。たくさんのクワガタの写真が並んでいて、お子さまたちがそれを写しています。すべて違う種類のクワガタかと思ったら、よく見るとタイトルに「ノコギリクワガタ」と書いてあるではありませんか。
「ええっっ!!」と、思わず声を出してしまったjimjim。お子さまたちの間から写真を覗き込みますと、同じ「ノコギリクワガタ」でも地方によって大きさも形も全然違うんです。そこには、jimjimが子どもの頃に出会った「ノコギリクワガタ」の写真もありました。「そうか、そういうことだったのか……」。お子さまたちに紛れて、妙に納得するjimjim。この年齢になって、ようやく「人生の疑問」のひとつが解明された瞬間なのでありました。お子さまたちに感謝です。

では、ここから「本題」に入りましょう。きょうのヨコハマキッズでは、「たべっ子どうぶつ探し」をしました。どういうゲームかといいますと、幼稚園の園舎の中に「たべっ子どうぶつ」に出てくるどうぶつの絵が貼ってあります。その絵を探して、スタンプラリーを完成させるというものです。
まずは、先生からルールの説明です。こちらは、年中さんのシーン。年中さんと年長さんは、自分で園舎の中を巡り、「どこに、どのどうぶつがいたか」を自己申告して、それが正しくないとシールはもらえないルールとなっています。

ということで、さっそく「どうぶつ探し」に出発するお子さまたち。

一方、年少さんはといいますと、こちらは先生が「絵」の近くまでお子さまたちを引率してくれます。

「さあ、このあたりに絵があるよ」と、先生から大ヒントが出ますとキョロキョロしつつもすぐに発見。時計の横にいたのは、「うさぎさん」でした。

こんな感じで、ホールに行けば「あったあった!!」と大よろこび。

その瞬間の目の輝きがたまりません。いいでしょう、一生懸命なんです。

年少さんは、先生がその場でシールをペタッ。

どんどんシールが溜まっていきます。
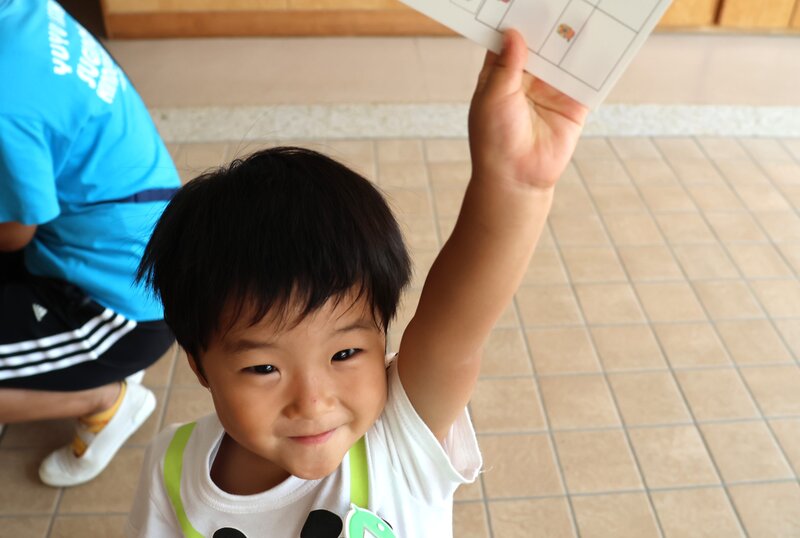
がんばるぞー!!

がんばったぞー!!

「どうぶつ」を探しながら、お子さまたちの真剣なまなざしに出会えた、きょうの「たべっ子どうぶつ探し」でした。
では、また明日お会いしましょう。
by jimjim
